| 建築保存としての違和感 |
| 新堀学 |
まずはじめに《孤風院》のこれまでの歴史と、関わった人々についてお話しいただけますか。 |
| 木島千嘉 |
《孤風院》は、もともと熊本高等工業学校の講堂として現在の熊本大学構内に1908(明治41)年に落成した建物でした。木造平屋のバシリカ式(長手方向に向かって内部に並ぶ2列の列柱が、長方形の平面を中央の身廊とそれを囲む側廊に分割される形式)平面で床面積が約100坪ありました。1974年に、当時熊本大学に勤務していた父(木島安史)は、《熊本地方裁判所》の赤レンガ本館の保存運動をきっかけに『熊本日日新聞』で「家は生きてきた──熊本の洋館・和館めぐり」という連載をしていたのですが、ちょうどその年、老朽化進行を理由にこの講堂の解体廃棄が決定されました。かつては天皇の行幸もあったようで式典の場としても活用されていたのでしょうが、70年代には運動部の溜まり場となりだいぶ荒廃していたようです。保存運動は結局失敗し、父は個人として移築保存することにして、講堂の払い下げを受けました。解体はしたものの、この規模の木造をそのまま残すには防火指定の問題もあるし、敷地購入の資金的な問題もあり、移築先の決定は難航したようです。最終的に阿蘇町が過疎対策として熊本大学の先生達にこのあたりを別荘地として誘致をしていたこともあり、この地に落ち着くことになりました。
|
|
 《孤風院》外観 《孤風院》外観 |
|
《孤風院-coffin》は、その際に父が命名したもので、その音韻は、英語で棺桶、フランス語では宝箱の意味を持ちます。移築にあたり、材料が傷んで不足したという理由もあったと思いますが、そのまま解体・復元というかたちはとっていません。基本的な外形は元の姿を踏襲していますが、講堂を住宅に変容させたプロジェクトとしてメディアにも発表していますし、内部に関しては意図的にあちこち空間操作を施しています。具体的には建物の長手方向を2スパン縮め正方形にするとともに身廊部分の床を側廊より低くして集中形式の平面構成に変えています。また舞台裏の講師控え室ゾーンを食堂・水廻り・寝室として改造し、入り口上部に4.5畳の和室と書斎コーナーを増設するなどしています。熊本大学に勤務していた期間、普段は自分ひとりのための、夏の間だけ一家揃って過ごす住居となり、同時に研究室のゼミやコンペ合宿が行なわれる分室的な使われ方もされていました。
1992年に父は亡くなり、その時《孤風院》は父のロマンが凝縮されたようなものだということで父を偲ぶ会を「孤風院の会」と名づけて、業績の整理や作品集の刊行事業などを主催し、ここでもレクチャーやシンポジウムを開きました。その後、7回忌をもって会はいったん解散しましたが、《孤風院》を維持するのには、とにかく使い続けてメンテナンスし続ける必要があります。年に何回か人が来て窓を開け、建物に風を通すだけでもずいぶん違うわけです。でも私たち家族は東京在住なのでそう頻繁に来るのは難しいことでしたし、補修メンテナンスといってもそもそも未完の状態から阿蘇の自然環境にさらされ傷みも進行していきますから、コストをはじめメンテの手を確保するのも難題でした。
一方で、父は熊本大学にずっと勤務して設計活動の一方で建築教育に力を入れていましたから、実習活動の場所として、ここを提供していくことが父の活動の一部を継承していくことになるし、建物自体の維持にもつながるのではないかという認識が家族のなかでもありました。特に、現実の建築設計では試行錯誤して失敗させてもらえる機会がない。また建築は本来時間をかけてつくり、手をかけ続け、活用され続けるべきものだと思いますが、そうしたことを具体的に検証学習できる場も少ない。例えば模型でも、海外では原寸で作ることもあるのでしょうが、日本の大学の建築学科はせいぜい1/50とかスタイロや白模型制作までが大半です。そこで《孤風院》という建物を実習・制作・創作の実験台として提供できれば、維持補修の一端を担ってもらいつつ、参加者にとっても新しい意義が見出せるものになるのでは、ということになりました。学生を含め建築空間に関心の高い人たちにとって、レクチャーを受ける場、暴露試験など持続性・実験・観察・観測の場、そこで音楽を奏でたり食事をしたりして空間の活用方法を体感し交流できる場となり、個人の所有物のままですが、ちょっと社会性・公共性をもつ特殊なスペースという位置づけをして、「つくり続ける」というワークショップの企画を毎年やろうという方向性がはっきりしたのが2000年くらいでした。再開継続された「孤風院の会」の活動の流れはそういったところです。
|
|
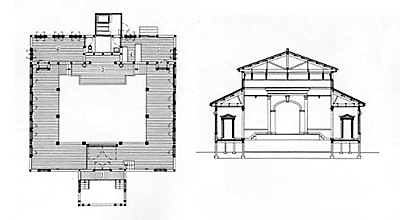 《孤風院》平面図、断面図 《孤風院》平面図、断面図 |
| 新堀 |
実際に移築を始めてからの家族の反応はどういったものでしたか?
|
| 木島 |
とにかくお金がないということもあり、父は未完成状態で使い始めて、例えば最初の年は広間とキッチンの間も間柱だけで透けて見え、天井も格子だけで面の部分が抜けた状態でした。毎年来るたびに「ボーナス」が投資されどこかが変わり、一つひとつ仕上がっていく感じでした。不便な所もありましたが、子供心にはここはそういう場所だ、ただ東京の家よりずっと大きい家だなという程度の感覚でした。オープンハウスの参加者のなかには他の洋館のように全体が綺麗に仕上がるのを期待されることもありましたが、家族としてはがらんとしたニューヨークのSOHOのようなロフト風の雰囲気も気に入っていたし、すべてが仕上がりきった状態を目指すイメージはなかったですね。いまもできる範囲で維持をし、手に余る部分は時の流れに沿って壊れても致し方ない、という感覚が家族のなかには正直あります。だから、ワークショップでいじることについては、不注意の火事などで孤風院が崩壊するのは受け容れ難いですが、実験や創作活動としてどんどん手を加えていくことは、どうぞどうぞ、というスタンスです。
|
| 新堀 |
そうして現在の活動へと動き出したわけですね。そのあたりから髙木さんが孤風院の会事務局代表として面倒を見られていると思いますが、当初はどういう方々が参加されていたのですか。
|
| 髙木淳二 |
最初の時期の参加者は、ほぼ木島研究室の卒業生で九州にいる人たちでした。それに加えて木島さんが熊本で生活しているあいだに親しくされていた人たちも参加していました。年代的には木島さんより5歳くらい上の人からで、木島さんとの個人的な関係の記憶をたくさん持っている人たちですね。
食事をつくる人とか音楽を奏でる人などと、人が多く集まってきたのは、おそらく7回忌からです。7回忌は、なんとなくそういうタイミングでした。木島さんが亡くなってからの6年間は楽しむような余裕はありませんでしたが、7回忌を境に、《孤風院》をもっと楽しもうじゃないかという気持ちが出てきました。関わってきた人を大きく分けると、7回忌以降は木島さんをまったく知らない世代がほとんどです。それまでは木島さんと直接面識のある人が大半でしたが、その比重が7回忌を境に変わりました。参加者の構成も、事務局の人達も転換していきました。参加者が変わってなにが変わったかというと、修理修繕・メンテナンスを主としながらも、新しい要素を付け加えていこうという動きが出てきて、学生さんが関わってきたことです。いまでは企画も学生がやっています。
7回忌前後といった時期は、われわれ自体がどうやってこれを維持していけばいいのかを模索していた時期です。そして、緊急を要するところを早くなんとかしなければという状況でしたから、維持管理に必要な技術の勉強をしていましたね。シロアリがきたらどうしたらいいのか、ペンキをどうやって塗るのか、明治と現代の塗装技術はどう違うのかとか、そういうことの勉強期間でした。技術を学ぶために職人さんを呼んでレクチャーをしてもらったりしました。学生のなかには職人さんのところへ夏休みに何日間か「留学」したりする者もいましたね。そしてその時期に、いまの活動に必要な仲間作りもしていました。道具や材料も集まり始めてきて、それが具体的な物作りに必然的につながっていきました。
|
| 木島 |
持主としては、部分的に壊しても、どんなことをしてもいいよというスタンスはあるのですが、企画者・参加者には《孤風院》の本体に手を入れることは、気が引けるところもありました。それで、まずは道具小屋を作って腕を磨いてから、初めて《孤風院》の本体のほうに手をかけることにしようかという企画になりました。また、いろいろな職人の方に指導していただき、ここまできていますが、最初は釘抜きの仕方もわからない建築学科の学生が集まったところでなにもできないかもしれないとか、1日で達成感の得られるワークショップじゃないと人が集まらないかもしれない、という感じがあったのですが、でも習えばなんとかなる、日数のかかる作業もなんとか運営できるというのが、ワークショップを通じて度胸がついたというか、わかってきました。» |
|
 木島千嘉氏 木島千嘉氏 |
 《孤風院》外観
《孤風院》外観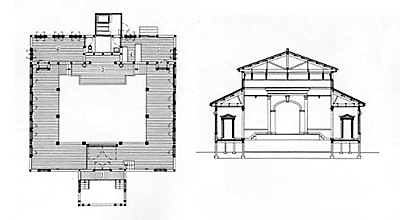 《孤風院》平面図、断面図
《孤風院》平面図、断面図 木島千嘉氏
木島千嘉氏